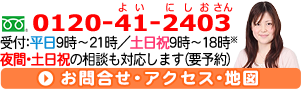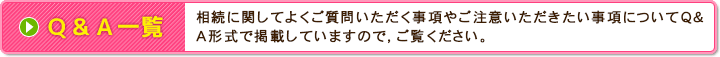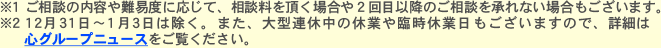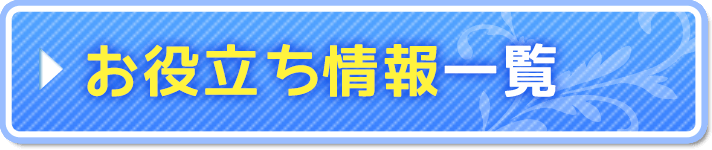生前贈与は遺留分侵害額請求の対象となるのか
1 生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となる場合もある
生前贈与は、使い方によっては相続税対策にもなるため、活用の幅が広い財産譲渡の手段です。
一方で、多額の財産を生前贈与してしまうと、他の相続人の遺留分を侵害してしまい、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
良かれと思ってした孫への生前贈与が、相続人の遺留分を侵害していると、相続人間のトラブルの原因となってしまうこともあり得るのです。
そこで、今回の記事では、「生前贈与は遺留分侵害額請求の対象となるのか」に焦点を当てて説明します。
2 生前贈与が遺留分侵害額請求の対象になるケース
遺留分侵害額請求の対象になるのは、原則、被相続人の相続開始前1年間に贈与されたものに限ります(民法第1044条第1項)。
しかし、条件によっては、「相続開始前1年間の贈与」以外の贈与についても、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。
ここでは、遺留分侵害額請求の対象になる生前贈与について見ていきます。
⑴ 遺留分の侵害を知ってした生前贈与
贈与する側(贈与者)および贈与される側(受贈者)の双方が、他の相続人の遺留分を侵害することを知った上で生前贈与を行なった場合について、民法は次のように定めています。
民法第1044条
第1項 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
第3項 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
つまり、贈与者・受贈者双方が遺留分の侵害を知っていた場合は、受贈者が相続人か否かにかかわらず、「相続開始前1年間の贈与」以外の贈与についても、期間制限なく遺留分侵害額請求の対象になるのです。
たとえ10年以上前の生前贈与であっても、遺留分侵害額請求の対象です。
⑵ 遺留分の侵害を知らずにした生前贈与
次に、遺留分の侵害を知らずにした生前贈与についてです。
こちらは、相続人への生前贈与か、相続人以外への生前贈与かによって扱いが変わります。
相続人への生前贈与
民法第1044条第3項にあるように、生前贈与が「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」や「生計の資本として受けた贈与」である「特別受益」とされる場合には、相続開始前10年以内の生前贈与が遺留分侵害額請求の対象になります。
民法改正前には期間の制限がありませんでしたが、改正により、相続開始前10年以内に限定されました。
なお、遺留分侵害額請求の対象となる「特別受益」とは、次のようなものがあります。
・婚姻や養子縁組のための贈与:結婚や養子縁組などで家を離れる者に対する財産の贈与(相続財産の分与に相当)
・生計の資本:独立している子などへの多額の贈与、例えば、住宅購入資金や事業資金等の贈与
ただし、挙式費用や生活費の負担については、一般的な扶養義務の履行の範囲内であれば、特別受益にはあたらないと考えられています。
遺留分と特別受益の持ち戻し免除との関係
各相続人の相続分は、この特別受益を相続財産に持ち戻して算定することになります。
※特別受益の「持ち戻し」とは、特別受益が認められる相続人がいる場合に、特別受益の金額が相続財産に含まれているとみなしたうえで、法定相続分と遺留分を計算することを意味します。
一方、被相続人が、特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をすると、持ち戻しの必要がありません。
相続分の計算においては、被相続人の意思を最大限尊重するという観点から、特別受益の持ち戻しの免除が認められているのです。
では、被相続人が特別受益の持ち戻しの免除の意思表示をした際の、遺留分の算定における特別受益の扱いはどうなるのでしょうか。
結論から言えば、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があっても、特別受益は相続財産に持ち戻して遺留分の算定をすることとなります。
遺留分とは、相続財産の処分の自由を制限し、相続人が最低限の遺産取得を保証する制度であることから、被相続人が持ち戻しの免除の意思表示をすることで、遺留分算定の際に相続財産に持ち戻さないとすると、遺留分制度の趣旨に反してしまいます。
最高裁判所は、平成24年1月26日の判決で次のように判示しています。
遺留分減殺請求により特別受益に当たる贈与についてされた持戻し免除の意思表示が減殺された場合、持戻し免除の意思表示は、遺留分を侵害する限度で失効し、当該贈与に係る財産の価額は、上記の限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、当該贈与を受けた相続人の相続分から控除されるものと解するのが相当である。
参考リンク:最高裁判所判例集
このことからも、被相続人の特別受益の持ち戻し免除の意思表示にかかわらず、特別受益は遺留分算定の基礎財産に含まれることがお分かりいただけるでしょう。
相続人以外への生前贈与の場合
相続人以外への生前贈与の場合は、原則通り、相続開始前1年間になされた贈与についてのみ、遺留分侵害額請求の対象となります(民法同1044第1項)。
3 遺留分侵害額請求をする際のポイント
前記で、遺留分侵害額請求の対象になる生前贈与について見てきました。
ここでは、実際に遺留分侵害額を請求する際の注意事項について説明します。
⑴ 遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権には消滅時効がありますので、注意が必要です。
遺留分侵害額請求権は「相続開始と遺留分を侵害する生前贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間」で時効を迎え、当該請求権が消滅してしまいます(民法1048条)。
また、相続が開始してから10年以内に遺留分侵害額請求権を行使しない時も、この請求権は時効により消滅します(民法1048条)。
例えば、相続開始3年目に遺留分侵害を知った場合は、遺留分侵害を知ってから1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しないと時効が成立します。
遺留分侵害を知ってから1年を過ぎてしまえば、相続開始10年以内であっても遺留分侵害額請求はできなくなります。
相続開始11年目に遺留分侵害を知った場合は、相続開始からすでに10年が経過して時効が成立しており、遺留分侵害額請求権は行使できません。
遺留分侵害を知った場合は、弁護士に相談して、なるべく早く遺留分侵害額請求権を行使することをおすすめします。
⑵ 遺留分侵害額請求の対象は金銭に限られる(民法改正)
遺留分侵害額請求権の対象遺産について、令和元年の相続法改正により、次のように改正されました。
改正前
「遺留分減殺請求権」といい、遺留分侵害を限度として、贈与や遺贈された財産の返還を請求することができる権利でした。(物を取り戻す権利)
改正後
「遺留分侵害額請求権」は、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利のことをいいます。(金銭を支払ってもらう権利)
この相続法改正により、侵害された物を取り戻す権利(遺留分減殺請求権)から、侵害された額相当の金銭を払ってもらう権利(遺留分侵害額請求権)に改正されていますので、不動産などの遺産そのものの返還を要求することはできなくなりました。
4 遺留分でお悩みの方へ
今回は、「生前贈与と遺留分侵害額請求」に焦点を当てて説明しました。
生前贈与は、原則、遺留分侵害額請求の対象に含まれますが、その対象範囲は、「遺留分侵害を知っていた場合」と「遺留分侵害を知らなかった場合」で違っており、また、受贈者が「相続人の場合」と「相続人でない場合」でも違ってきます。
遺留分侵害額請求を行使するためには、生前贈与によって遺留分を侵害されていることを知ってから、証拠を集め、財産評価を行い、遺留分侵害額の計算や侵害した者との交渉も行わないといけません。
また、遺留分侵害額請求には時効もありますので、専門知識や経験・ノウハウがないとスムーズに進めるのは困難と考えられます。
遺留分侵害額請求をお考えの方はもとより、自分が遺留分侵害をしているかもしれないとお悩みの方、どこまでの生前贈与が対象に含まれるのか分からないという方などは、相続に注力している法律事務所にご相談されることをおすすめします。
遺産相続で財産が家しかない場合、どうやって遺産分割するか 土地の相続手続・登記の流れ